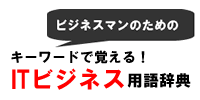行動経済学とは
【読み】 こうどうけいざいがく
【意味】
行動経済学とは、人は感情にもとづき意思決定をするという前提をもとに、人の購買行動や消費者心理を研究することを目的とした経済学をいう。
行動経済学は、古典的な経済学が前提としている経済人による合理的な意思決定をするのではなく、感情にもとづく非合理的な意思決定をすることを前提としている。
行動経済学は、商品やサービスの訴求などの場面で活用できるため、外食やサービス業などの現場で実践されている。
一心理学者であったダニエル・カーネマンが、多数の実験をもとに、現実の人間は、不確実性の下では必ずしも合理的な意思決定をしないことを実証し、古典経済学の「期待効用理論」に替わる理論として「プロスペクト理論」を唱えたことが行動経済学が生まれる契機となった。
行動経済学でよく知られる例に「フレーミング効果」や「保有効果」などがある。
「フレーミング効果」は、同じ内容でも質問や問題の提示のされ方によって、異なる受け止め方をし、意思決定の選択・選考がまちまちになることをいう。
たとえば、医師が患者に手術の受けさせる際に「生存率95%」というか、「死亡率5%」というかでは受け取る印象が異なってくる。
また、「保有効果」は、自分が所有しているものに高い価値を感じ、手放したくないと感じる現象である。
行動経済学の入門書として『ねじれ脳の行動経済学』(古川雅一)がある。
【カテゴリー】
【関連キーワード】
入門 学会 論文 大学
【右脳で覚える!目で見るキーワード・マインドマップ】

更新日:2011/11/07